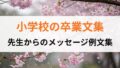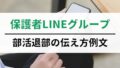運動会で近年よく見かけるのが「ソーラン節」の演舞。
力強い動きと迫力のある掛け声が特徴で、見ごたえのある演目として、全国の学校で取り入れられています。
しかし、
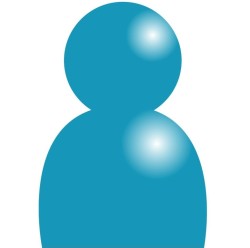
どうして運動会でソーラン節を踊るんだろう?
と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ソーラン節が運動会で踊られるようになった理由について、わかりやすく解説します。
子どもたちがなぜこの伝統的な踊りに取り組むのか、その背景を知るきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ運動会でソーラン節を踊るのか?

「南中ソーラン」の誕生と全国への広がり
運動会でソーラン節が踊られるようになったきっかけは、1991年。
北海道・登別市立幌別小学校で「南中ソーラン」が発表されたことが始まりです。
これは、北海道の民謡「ソーラン節」に現代的な振り付けやアレンジを加えた創作ダンスで、迫力のある動きと力強い掛け声が特徴でした。
この演目は、地域の行事で披露されたことをきっかけに話題を呼び、少しずつ道外にも広がっていきます。
特に、全員で動きをそろえて踊る構成は、団体演技にぴったり。
クラスや学年ごとの発表に適していたことから、運動会の演目として多くの学校に取り入れられるようになったのです。
テレビドラマでの紹介が認知を後押し
「南中ソーラン」が全国的に知られるようになった大きなきっかけ。
それは、2001年放送のテレビドラマ『3年B組金八先生(第6シリーズ)』です。
劇中では、生徒たちが「南中ソーラン」に挑戦し、真剣な表情で踊る姿が感動的に描かれました。
その影響で、視聴者の間でソーラン節の認知度が急上昇。
「ソーラン節=団結、青春の象徴」
といったイメージが強まり、学校教育の現場でも注目されるようになりました。
そして、テレビを通じて、広く一般に知られるようになり、ソーラン節は「運動会の定番」として全国に定着していったのです。
学校が運動会でソーラン節を選ぶ3つの理由

ソーラン節が広まったきっかけは確かにありますが、それだけで全国の学校が今も採用し続けているわけではありません。
多くの学校が運動会の演目としてソーラン節を選ぶのには、明確な理由があります。
ここでは、特に代表的な3つのポイントをご紹介します。
団結力・チームワークが表現しやすい
ソーラン節は、全員が力強く、同じ動きをそろえて踊ることで、ひとつの大きなパフォーマンスになります。
そのため、練習を通して自然と「協力する力」「仲間との一体感」が育まれます。
その結果、子どもたちにとって大きな達成感が得られるのです。
クラスや学年全体の団結力を高める目的で選ばれることが多いのも納得です。
和の文化を取り入れた教育的意図
ソーラン節は、もともと北海道の民謡がルーツです。
現代風にアレンジされているとはいえ、伝統的な日本文化を子どもたちに体験させることができる点も、教育的な価値があると評価されています。
グローバル化が進む時代だからこそ、自国の文化に触れる機会を大切にしている学校も少なくありません。
保護者ウケが良く、見栄えもする
運動会は子どもたちだけでなく、保護者や地域の人々にとっても楽しみにされているイベントです。
ソーラン節の迫力ある動きや真剣な表情は、見ている側にも感動を与えやすく、写真やビデオ映えもします。
そうした“見栄え”の良さも、選ばれる理由の一つになっていると思われます。
まとめ
今回は、なぜソーラン節が運動会で踊られるようになったのか、その理由についてご紹介しました。
ソーラン節が運動会で踊られるのは、ただの流行ではありません。
「南中ソーラン」から始まり、テレビドラマでの紹介もあって、全国に広がっていきました。
そして、団体でそろえて踊るからこそ生まれる一体感や、和の文化にふれる機会として、今も多くの学校で選ばれているのです。
これからも、運動会で子どもたちの元気と一体感を表現する定番演目として、親しまれていくことでしょう。