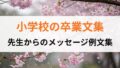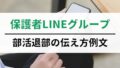夏休みに入ってから、ずっと家で過ごしている高校生。
そんな子どもの様子に、なんとなく不安を感じている保護者の方もいるかもしれません。
- 「このままで大丈夫…?」
- 「もっと外に出たほうがいいのでは?」
と悩むこともあるでしょう。
そこで本記事では、高校生が夏休みに家にずっといる理由と、親としてできる関わり方のヒントをわかりやすくお伝えします。
お子さんとの関係をよりよくするきっかけとして、ぜひ参考にしてみてください。
高校生が夏休みにずっと家にいる4つの理由

ここでは、よくある5つの理由をわかりやすく紹介します。
勉強や部活からの解放で「休みたい」
普段、学校生活は意外とハードです。
特に、朝練や放課後の部活がある人は、授業や宿題にくわえて、とにかく大変です。
そんな中でやっとやってきた夏休み。
「とにかく休みたい」と感じるのは自然なことです。
家でゴロゴロしたり、昼まで寝たりするのは、体が「ちょっと休ませて」と言っているサインかもしれません。
友人関係の悩んでいる
など、友人関係で悩みを抱える人もいます。
そんなときは、「どうせ行く相手もいないし…」と感じてしまい、外出する気持ちがわかなくなるのです。
インドア趣味が中心(ゲーム・動画など)
最近は、家で楽しめることがたくさんあります。
たとえば、
- YouTube
- Netflix
- ゲーム
- SNS
など、スマホ一つで一日中楽しめる時代です。
外に出なくても退屈しない環境が整っているからこそ、
「わざわざ暑い中、外に出る理由がない」
と感じてしまうのです。
これは怠けているというより、「家での過ごし方のバリエーションが増えた」とも言えます。
外出先がない/お金がかかる
現在では、このように感じている高校生も少なくありません。
特に都市部以外では、移動手段が限られていたり、気軽に遊べる場所がなかったりします。
電車賃やカフェ代がかかると思うと、「やっぱり家でいいや」となりやすいのです。
夏休みにずっと家にいても放っておいてもいいケース

「夏休み、家でゴロゴロしてばかりだけど…このままで大丈夫?」
と、保護者の方が心配になることもあるかもしれません。
しかし、すべての“引きこもり”が悪いわけではありません。
ここでは、放っておいても大丈夫な3つのサインを紹介します。
食事・睡眠が安定している
朝昼晩の食事をとっていたり、夜にきちんと眠れているなら、本人なりのペースで生活を送れていると考えられます。
たとえ外に出なくても、
- 毎日なんとなく決まった時間にごはんを食べている
- 昼夜が大きく逆転していない
- 食事に関心がある
といった様子があるなら、極端に心配する必要はないかもしれません。
特に高校生は、成長期の疲れを感じやすい時期です。
自分のペースでしっかり休んだり、ごはんを食べたりすることも、夏休みならではの過ごし方のひとつと言えるでしょう。
家族と会話がある
ちょっとした会話があるかどうかも、大きな安心ポイントです。
たとえば、
といった一言があるかないかだけでも全然違います。
家族とやりとりができている様子があれば、気持ちの面でも落ち着いて過ごせている可能性があります。
趣味に打ち込んでいる(ゲーム・読書なども含む)
- ゲームばっかりしてる
- 動画ばっかり見てる
といった姿を見ると、つい注意したくなるかもしれません。
しかし、それが本人にとって、大事な“楽しみ”や“息抜き”である場合も多いです。
特に、
- ゲームをじっくりやり込んでいる
- 好きな本やアニメに夢中になっている
- 創作活動(絵、音楽、プログラミングなど)をしている
といった様子があれば、それは立派な「趣味に打ち込んでいる」時間。
何かに集中して楽しめているということは、心が安定しているサインでもあります。
夏休みにずっと家にいて注意が必要なケース

保護者の方が「何か様子が違うかも」と気づくきっかけになりそうなケースをご紹介します。
昼夜逆転や極端な引きこもりが続いている
夜ふかしして、昼ごろに起きる生活は、夏休みにはよくあることです。
しかし、
- 朝方まで起きていて昼過ぎまで寝る生活が何日も続いている
- 一日中まったく部屋から出ない日が続く
といった場合、少し気をつけて見てあげましょう。
本人も「なんとなくしんどい」「外に出るのが面倒」と感じて、悪循環にはまっている場合もあります。
家族との会話がほとんどない
普段はちょっとしたことでも話していたのに、
- 急に返事をしなくなる
- 会話を避けるようになる
といった場合、心に何か抱えている可能性があります。
もちろん、話したくない時期もあるとは思います。
しかし、「完全にシャットアウトしているように見える」ときは、少し気にかけてみましょう。
スマホやゲームに依存している様子が強い
スマホやゲームが好きなのは自然なこと。
しかし、
- 食事中もスマホを手放さない
- 寝る直前までゲームをしている
- スマホを取り上げようとすると極端に怒る
などの様子が見られると、少し依存気味になっている可能性もあります。
もちろん、好きなことに夢中になるのは悪いことではありません。
しかし、他のことが手につかなくなるほどだと、生活全体のバランスが取りにくくなってしまいます。
夏休み中の高校生への関わり方|親が取るべきアプローチ
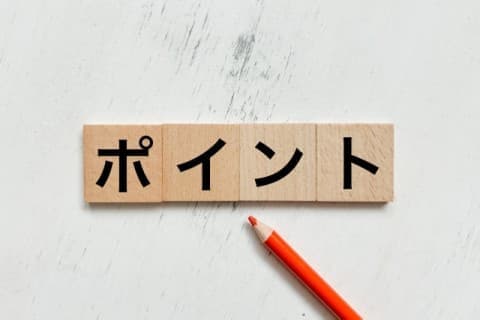
ここでは、親としてどう接するか?
見守りとサポートのバランスを取るアプローチを5つご紹介します。
無理に外へ出そうとしない
- 「外に出なさい」
- 「友達と遊びに行ったら?」
という声かけは、一見正しそうに思えます。
ですが、無理に外へ促すと、プレッシャーに感じて逆効果になることもあります。
本人にとっては、
- 「出る理由がない」
- 「気が進まない」
など、本人なりの事情があるかもしれません。
ですから、本人が「どうしたいか」を尊重してあげましょう。
外出を強要せず、気持ちが動くのを待つという姿勢も大切です。
安心して話せる「聞き役」になる
高校生は思春期のまっただ中。
何でも話してくれる年齢ではなくなりますが、心のどこかで“親に聞いてほしい”という気持ちを持っていることも多いです。
そのため、無理に質問攻めにするのではなく、
といった、さりげない声かけをしてみましょう。
すぐに答えが返ってこなくても、話したくなったときに思い出してもらえるような「安心して話せる存在」であることが大切です。
家でできる活動を一緒に探す
外出しなくても、家の中で充実した時間を過ごせる方法はたくさんあります。
例を挙げると、次のようなものがあります。
- 一緒に映画を観る
- 料理を手伝ってもらう
- DIYや片づけをする
- 簡単な運動やストレッチをしてみる
こうした「ちょっとした共同作業」を通して、自然な会話や笑顔が生まれやすくなります。
本人が興味を持てそうなことを、一緒に探す姿勢も大切です。
「あなたを気にかけてる」姿勢を見せる
干渉しすぎるのは逆効果ですが、まったく関心を示さないと「無関心」と受け取られてしまうこともあります。
なので、たとえば、
- 「今日のごはん何がいい?」と聞く
- 好きそうなアイスを買っておく
- そっと飲み物を置いておく
といった小さな行動でも、「ちゃんと気にかけているよ」というメッセージは十分に伝わります。
声をかけるよりも、“行動”で伝えるほうが受け入れられやすい場面もあるのです。
まとめ
今回は、高校生が夏休みに家にずっといる理由と、親としてできる関わり方などをご紹介しました。
高校生が夏休みに家にいるのは、休息や趣味を楽しんでいるなど、自然な理由であることも多く、必ずしも心配する必要はありません。
食事をとっていたり、家族と会話があるようなら、無理に外出を促す必要はないでしょう。
ただし、
- 極端な昼夜逆転
- 会話の減少
などが続く場合は、そっと様子を見守りながら、安心して話せる環境づくりを意識してみてください。
焦らず、親子それぞれのペースを大切に過ごせるといいですね。