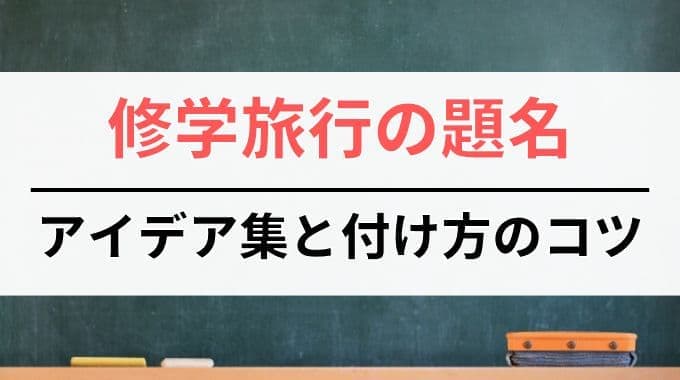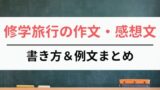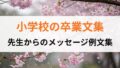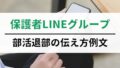修学旅行が終わると、提出することになる「作文」や「感想文」、「レポート」。
しかし、いざ作成しようとするも、
- 「題名が全然思いつかない…。」
- 「ありきたりなタイトルになっちゃいそう…。」
と悩んでしまう方も少なくないはず。
そこで本記事では、修学旅行の作文・感想文・レポートにぴったりな題名のアイデアや付け方のコツを、わかりやすくご紹介します。
修学旅行の思い出を、より上手に伝えるためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてくださいね。
修学旅行の「作文」の題名の付け方と例
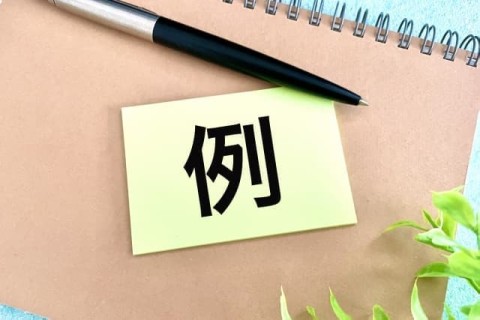
「作文」における題名のポイント
作文の題名を考えるときは、次の2つのポイントを意識してみてください。
① 内容の中心をはっきりさせる
「どこで」「何をした」「何を感じた」ということが伝わるようにしましょう。
たとえば、ただ「修学旅行」とだけ書くよりも、どこでどんな体験をしたかがわかる方が、その後の文章も読みたくなりますよね。
② 読む人が気になるような言い方にする
- 「ちょっと面白そう」
- 「この人、何を感じたんだろう?」
と思わせるような、少しだけ気持ちを込めた言い方にするのもポイントです。
まじめすぎず、でもふざけすぎず、あなたらしい言葉で表現するのが大事です。
「作文」の題名のテンプレートと例
ここでは、実際によく使える「題名のテンプレート」と、それに合った例を紹介します。
自分の体験に合わせて、置きかえてみてください。
- 「京都で見つけた昔の日本」
- 「鎌倉で見つけた静けさと歴史」
- 「金沢で見つけた伝統のぬくもり」
- 「広島で平和を考えた日」
- 「奈良で鹿とふれあった日」
- 「東京で未来を感じた日」
- 「奈良に学んだ歴史の重み」
- 「戦争資料館に学んだ命の重さ」
- 「防災センターに学んだ備える力」
題名をつけるときは、まず自分が一番印象に残っていることを思い出してみましょう。
「楽しかった」「おいしかった」などの気持ちも大事ですが、それだけでなく、
「どんな気づきがあったか?」
を考えると、いい題名が見つかりやすくなりますよ。
修学旅行の「感想文」の題名の付け方と例

「感想文」における題名のポイント
修学旅行の感想文では、「何をしたか」よりも「どう感じたか」が大切です。
だから、題名にもあなたの気持ちや心の動きが表れるようにすると、読む人の心に残りやすくなります。
ここでは、2つのポイントを紹介します。
① 心の動きを表す言葉を使おう
- 「感動した」
- 「びっくりした」
- 「考えさせられた」
- 「学んだ」
など、そのときの気持ちをはっきり伝える言葉を使ってみましょう。
たとえば、「民泊が楽しかった」だけよりも、
「人のあたたかさに感動した」
と書いたほうが、読み手に気持ちが伝わります。
② 一番心に残ったことをしぼろう
全部の思い出を題名に詰めこもうとすると、ぼんやりした印象になってしまいます。
そのため、特に印象に残った場面をひとつ選んで、その気持ちにフォーカスすると、ぐっと良い題名になります。
「感想文」の題名の型と例
では、実際に使える「題名の型」と、その例を紹介します。
自分の体験に合わせてアレンジしてみましょう!
- 「沖縄の海に感動した私」
- 「五重塔に感動した私」
- 「民宿のおもてなしに感動した私」
- 「民泊体験から考えた人とのつながり」
- 「班別行動から考えたチームワークの大切さ」
- 「お寺体験から考えた心の落ち着き」
- 「東京見学で気づいた日本の多様性」
- 「歴史街道で気づいた日本の美しさ」
- 「新幹線の中で気づいた友だちとの絆」
感想文の題名は、あなたの気持ちや心の変化をギュッとまとめた「タイトル」です。
難しく考えすぎず、「一番心に残ったこと」を思い出しながら、正直な気持ちを表す言葉を使ってみてください。
修学旅行の「レポート」の題名の付け方と例

「レポート」における題名のポイント
修学旅行で書く「レポート」は、感想文や作文とはちょっと違う書き方をします。
一番のポイントは、自分の気持ちよりも、「何を調べたか」「何を学んだか」をしっかり伝えることです。
レポートの題名を考えるときは、次の2つを意識するとわかりやすくなります。
① 客観性・情報性を意識しよう
レポートは、事実や調査した内容を元に書く文章なので、題名も「情報が伝わる言い方」にしましょう。
「楽しかった」「びっくりした」などの気持ちよりも、
「どこで何を見て、どんなことを学んだのか?」
これが分かるタイトルが理想です。
② 学習目的を反映しよう
学校の授業や学びに関係のある内容が中心になるので、
- 「歴史」
- 「文化」
- 「防災」
など、学びのテーマがはっきりわかる題名をつけるのがポイントです。
「レポート」の題名の型と例
- 「清水寺の歴史と現在」
- 「金閣寺の歴史と現在」
- 「浅草の商店街の歴史と現在」
- 「金沢市の町づくりについての調査」
- 「京都市の景観保全の取り組みについての調査」
- 「奈良県の観光と自然保護の取り組みについての調査」
- 「平和記念資料館見学を通して考えた戦争と平和」
- 「防災センター見学を通して考えた災害への備え」
- 「江戸東京博物館見学を通して考えた暮らしの変化」
作文や感想文より少しかたいイメージのあるレポート。
ですが、調べたことを分かりやすく伝えることが目的なので、題名もシンプルでOKです。
題名をつけるときの共通アドバイス

「正直、題名ってどうでもいいし…」
こう思っている人もいるかもしれません。
しかし、あまりに適当すぎると、先生から
『やる気がないな…』
と思われてしまう可能性があります。
なので、とりあえずOKがもらえるラインを超えるために、最低限これだけは気をつけよう!というポイントを説明します。
内容がすぐ伝わる題名を目指す
先生に提出するための作文やレポートなら、“ひと目で内容が伝わる題名”をつけるのが一番大切です。
読み手に「きちんと書いてくれたのかな?」と思ってもらえるように、
- 「どこで」
- 「何をして」
- 「どう思ったか」
のうち、1つでも入れておくと安心です。
たとえば、
- 「広島で平和について考えた日」
- 「金沢の伝統にふれた体験」
のようにすれば、中身がすぐに伝わります。
オリジナリティのある言葉を使う
「オリジナリティ」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、自分の言葉で少し工夫するだけでOKです。
たとえば、他の人も「京都でお寺を見学した」と書いていたとしても、
- 「どのお寺が印象的だったのか」
- 「どんなふうに感じたのか」
などは、あなたにしか書けない体験です。
「清水寺の坂道で感じた昔の風景」など、ちょっとだけ視点を変えて書くだけで、オリジナリティが出てきます。
みんなと同じように見える内容でも、「自分の体験」を入れることで、先生の目にもとまりやすくなりますよ!
よくある質問(FAQ)

Q1. 題名は長くてもいい?
長すぎると読みづらいし、短すぎると内容が伝わりません。
目安は「15~25文字くらい」がちょうどいいと言われています。
自分が何を伝えたいのかが、パッと見て分かるくらいの長さを意識してみましょう。
Q2. 印象的な言葉が出てこないときは?
そんなときは、まず旅行中に一番心に残ったことを思い出してみましょう。
「一言でまとめると、どんな体験だった?」
と考えると、自分らしいキーワードが見つかるはずです。
写真を見返したり、友だちと話してみるのもヒントになります!
まとめ
今回は、修学旅行の作文・感想文・レポートに使える題名のアイデアや、上手な付け方のコツを紹介しました。
題名は、最初に読まれる大事なポイントです。
シンプルでもいいので、「どこで」「何をして」「どう感じたか」が伝わるようにしましょう。
そして、自分だけの体験や気持ちを少し入れるだけで、グッと伝わる題名になります。
もし、題名で悩んだ時は、この記事で紹介した型や例を参考にして、自分らしいタイトルをつけてみてくださいね。
ちなみに、以下の記事では、感想文・レポートなどの書き方や例文についてまとめているので、良ければ参考にしてみてください。