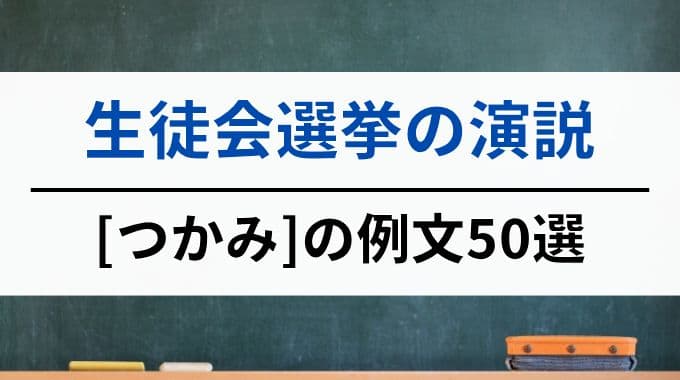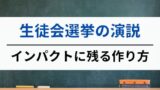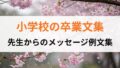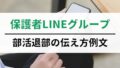生徒会に立候補するときに避けて通れないのが「演説」。
この機会だからこそ、多くの人に自分の思いをしっかり伝えたいと考えている方も多いでしょう。
とはいえ、
- 「何から話し始めたらいいのか分からない…」
- 「最初がうまくいかないと、緊張して全部グダグダになりそう…」
と不安に思っている人も少なくないはず。
そこでこの記事では、生徒会演説の“つかみ”に焦点をあてて、注目されやすい冒頭のアイデアやコツをわかりやすく紹介します。
自分らしい演説を届けるためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
生徒会演説で成功する「つかみ」のパターン5選

ここでは、演説の冒頭で使える、効果的な「つかみ」のパターンを5つ紹介します。
伝えたい内容に合ったものを選んでみてくださいね。
① ユーモアで笑いを引き出す
ちょっとした笑いを入れて、会場の雰囲気をやわらかくする方法です。
たとえば、
- 自分の失敗談
- ちょっとしたネタ
などを話すことで、聞いている人の緊張もやわらぎますし、自分もリラックスしやすくなります。
ただし、笑わせようと無理をする必要はありません。
自分らしい、自然な一言で大丈夫です。
「実は、今日のために5回も練習しました。でも緊張しすぎて、朝ごはんを食べるのを忘れました。」
笑ってもらえると、そのあとの話も聞いてもらいやすくなります。
② 自分のエピソードを話す
自分の体験や思い出を話すことで、親しみを持ってもらう方法です。
この方法を行うことで、聞く人は「どんな人なんだろう?」と興味を持って聞いてくれます。
自分がどんな経験をして、なぜ生徒会に立候補しようと思ったのかを、短く話すことで共感を得られます。
「私はもともと目立つのが苦手で、発表のときも声が小さかったんです。でも、去年の学校行事で、自分の意見が誰かの役に立った経験をして、自信がつきました。」
自分らしいエピソードは、演説に深みを与えてくれます。
③ 聞いている人に問いかける
質問を投げかけて、聞き手の気持ちをこちらに向ける方法です。
ただ話すだけではなく、「あなたならどう思う?」と問いかけることで、聞いている人を話に引き込むことができます。
難しい質問ではなく、誰でも考えやすい内容にしましょう。
「みなさん、毎日の学校生活で『もっとこうなったらいいのに』って思うこと、ありませんか?」
問いかけは、心の中で「あるある!」と反応してもらうきっかけになります。
④ 意外な事実や数字で引きつける
「えっ、本当に?」と思うような情報を最初に出して、興味を引く方法です。
たとえば、
- ちょっとした統計
- 学校に関する豆知識
などを入れると、「続きを聞いてみたい」と思ってもらえます。
ただし、数字などの情報は正しいものを使うようにしましょう。
「去年1年間で、生徒から学校への意見・要望が50件以上届いていたことを知っていますか?」
聞き手の興味を引きたいときに、こうした話題はとても使いやすい方法です。
⑤ 名言や印象的な言葉を使う
有名な人物の言葉や、自分が感動した言葉を紹介して始める方法です。
名言は聞く人の心に残りやすく、そこから自分の思いや考えに自然に入っていくことができます。
引用するだけでなく、「なぜその言葉に共感したのか」も一緒に伝えると良いです。
「“小さな一歩が、大きな変化につながる。”この言葉を聞いたとき、自分にもできることがあるんじゃないかと思えました。
今の学校をもっと良くするために、僕はまず自分から動こうと思い、生徒会に立候補しました。」
まじめで落ち着いた印象を与えたいときにおすすめです。
生徒会演説で実際に使える「つかみ」の例文50選

ここでは、中学生・高校生でも使いやすい「つかみ」の例文を、タイプ別に紹介します。
そのまま使ってもOKですし、自分の言葉に少し変えてアレンジしてもOKです。
大切なのは「自分らしさ」が伝わることです。
ユーモアタイプ例10選
緊張をほぐしたり、会場の空気をやわらかくしたい人向けです。
- 「緊張しすぎて、さっきまで演説の紙を上下逆に持ってました。」
- 「母に“笑顔で話してきなさい”と言われたので、今日の私は100%笑顔モードです。」
- 「心臓の音がマイクに拾われてないか心配です。」
- 「さっきまで“立候補やめようかな…”と思ってました。でも今ここにいます!」
- 「朝ごはんを食べてきたのに、緊張でまたお腹がすきました。」
- 「演説って、“自分で自分をアピールする時間”って、ちょっと恥ずかしいですよね。」
- 「すみません、原稿を3回書き直しました。これがベストバージョンです。」
- 「これからの数分間、どうか温かい目で見てください。」
- 「立候補したのは、友達に“やってみたら?”って言われたのが始まりです。責任感じてください(笑)」
- 「“立候補する勇気はある。でも話す勇気は別だ…”って昨日の自分が言ってました。」
エピソードタイプ例10選
自分の体験を通じて、思いや考えを伝えたい人向けです。
- 「私は小6まで、学校のルールって“守るだけのもの”だと思っていました。でも今は、みんなで作るものだと思っています。」
- 「去年、行事のことで意見を出したときに“ありがとう”って言われて、嬉しかったのを覚えています。」
- 「中1のとき、人前で話すのが苦手で、自己紹介でさえ手が震えていました。」
- 「友達が困っていたとき、“もっとこういう制度があればいいのに”と思ったことが、生徒会に興味を持ったきっかけです。」
- 「以前、生徒会の先輩の演説を聞いて、“私もこうなりたい”と思いました。」
- 「廊下のゴミを拾ったとき、“ありがとう”と声をかけられて、学校の温かさを感じました。」
- 「普段は目立つタイプじゃないけど、“誰かの役に立ちたい”という気持ちはずっと持っていました。」
- 「去年の体育祭でのトラブルをきっかけに、“もっと良くできるはず”と思うようになりました。」
- 「友達と“もっと意見が通るといいよね”と話したのが、この演説の出発点です。」
- 「私は“言われたことをやる人”ではなく、“やるべきことを考える人”になりたいと思っています。」
質問・問いかけタイプ例10選
聞く人の関心を引き、共感を誘うスタイルです。
- 「みなさん、学校生活で“もっとこうなったらいいのに”って思ったことありませんか?」
- 「“こんな校則、ちょっと変かも…”と思ったこと、ありますか?」
- 「もし今の学校を1つだけ変えられるとしたら、あなたは何を変えますか?」
- 「朝のあいさつ、ちゃんと返ってきていますか?」
- 「学校って、本当に“みんなにとって”居心地がいい場所でしょうか?」
- 「意見を出す場って、十分にあると思いますか?」
- 「誰かが困っているとき、助けられる環境って今の学校にありますか?」
- 「“生徒会”って、自分に関係あると思いますか?」
- 「行事のとき、準備が大変だったと思ったこと、ありませんか?」
- 「“学校をもっと楽しくしたい”って、心のどこかで思ったことありませんか?」
意外な事実・数字タイプ例10選
話への興味を引く導入文です。
- 「去年、生徒会に提出された意見のうち、半分以上が“知られていないまま”でした。」
- 「昨年度、学校で拾われた落とし物は130個以上。平均すると3日に1回です。」
- 「校内アンケートで、“行事の準備が大変だった”と答えた人は全体の6割以上でした。」
- 「朝の“おはよう”が返ってこなかった経験、ある人は80%以上だそうです。」
- 「今の校則、実は10年前から一度も見直されていないものもあるんです。」
- 「去年の生徒会の活動報告、見た人は全体の3割に満たないそうです。」
- 「意見箱に入った提案のうち、実際に採用されたのは10%以下でした。」
- 「先生に話しかけにくいと思っている生徒は、実は思っているより多いんです。」
- 「生徒会選挙の投票率は、年によっては70%を下回ることもあります。」
- 「文化祭のアンケートで、“もっと自由な企画がしたい”という声がたくさんありました。」
名言タイプ
落ち着いた印象で、思いの強さや考えを伝えたい人向けです。
- 「“変化を望むなら、まず自分がその変化になれ。” この言葉に背中を押されて、立候補を決めました。」
- 「“あきらめなければ、道は開ける。” この言葉を信じて、今日ここに立っています。」
- 「“声を出さない意見は、届かない。” この言葉が、自分を動かしました。」
- 「“学校は生徒のもの。” 当たり前だけど、忘れがちなことだと思いませんか?」
- 「“行動する人が、未来をつくる。” だから、私は立候補しました。」
- 「“誰かがやるのを待つんじゃない、自分がやるんだ。” 今の自分にぴったりな言葉です。」
- 「“自分にできることを、一生懸命やるだけ。” そんな気持ちで立っています。」
- 「“みんなが少しずつ変われば、大きな変化になる。” それを信じています。」
- 「“伝える勇気があれば、世界は変わる。” 今日はその第一歩です。」
- 「“挑戦しない理由より、挑戦する理由を探そう。” それが、今日の私のテーマです。」
【生徒会演説】つかみの後につなげる話し方のコツ

演説で「つかみ」がうまくいったとしても、それで安心してはいけません。
聞いている人の気持ちを引きつけた後は、その流れを自然につなげて、自分の考えや提案をしっかり伝えることが大切です。
ここでは、「つかみ」から本題にスムーズに入っていくための話し方のコツを紹介します。
① 話の流れに“つながり”を持たせる
つかみのあとに、いきなり話を変えないようにしよう。
つかみで笑わせたり注目を集めたりしても、そのあとで急に話題が変わると、聞いている人は「え?」と戸惑ってしまいます。
なので、
「ここからは真面目な話をします」
など、少しだけ気持ちを切り替える言葉を入れると、自然に話が進みます。
「……と、ちょっとふざけた話から始めましたが、ここからは僕の本気の気持ちを聞いてください。」
② 「なぜこの話をするのか」を伝える
「どうしてこの話をしたいのか」をはじめに伝えると、聞き手も納得しやすくなります。
ただ意見を言うだけでなく、その理由やきっかけを話すことで、「なるほど、そういうことか」と思ってもらえます。
自分が体験したことや、日ごろ思っていることを少し話すのがポイントです。
「僕がこの話をしようと思ったのは、去年の学校行事で気になったことがあったからです。
③ 聞く人に関係があることだと伝える
「この話は、みんなにも関係があります」と伝えると、よく聞いてもらえます。
自分の意見だけを話すよりも、
「この話はあなたにも関係がある」
と伝えると、聞いている人が自分のこととして考えやすくなります。
そのため、「学年」や「立場」を意識して話すことで、より親しみやすくなります。
「これは特に1年生のみなさんに関係のある話です。入学したばかりで、不安に感じることも多いと思います。」
まとめ
今回は、生徒会演説の“つかみ”に焦点をあてて、冒頭のアイデアやコツをわかりやすく紹介しました。
生徒会演説の「つかみ」は、話の聞き手を引きつける大事な最初の一歩です。
ユーモアやエピソード、問いかけや名言など、いろいろな方法がありますが、大切なのはあなたらしく伝えること。
紹介した例文やコツを参考に、自分に合った“つかみ”を見つけて、演説のスタートから自信を持って話してみてください。
ちなみに、「つかみ」以外でインパクトに残る演説をしたい方は、以下の記事を参考にしてみてください▼